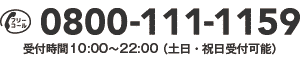以下のいずれかに該当する場合、お子さんはゲーム障害(ゲーム依存症)予備軍かもしれません。
- 他のことをしているときもゲームのことを考えてしまう
- ゲームができないと情緒不安定になり、怒ったりイライラしたりする
- ゲームのプレイ時間が平日で1日6時間を超える日がある
- ゲームを自らやめることができない
- ゲーム以外のことへの興味がなくなった
- 日常生活や学習に支障が出ているのにゲームをやめられない
- ゲームのプレイ時間を隠したり、実際より少なくごまかす
- 嫌なことがあったときに現実逃避をするためにゲームをする
- 人間関係や学校生活よりもゲームを優先する
※DSM-5のインターネットゲーム障害の診断基準を元にしています。
近年、ゲームの“娯楽性”だけでなく、“競技性”に注目した「eスポーツ」が社会的に認知され、ゲームのプラスの側面に焦点があたっています。
一方で、過度にゲームをすることは「ゲーム障害(ゲーム依存症)」に繋がるリスクがあります。
WHO(世界保健機関)は、「ゲーム障害とは、ゲームをすることが制御できず、他の生活上の利益や日常の活動よりもゲームをすることが優先され、生活や学業に支障が出てもゲームがやめられないこと」と定義しています。
2017年の厚生労働省の調査では、インターネットゲーム依存を含む「ネット依存」が疑われる中高生で約93万人いるとのデータがあります。
ゲーム障害(ゲーム依存症)の様々な要因
-
1努力の割に報酬が得られる
人は課題をクリアすると快楽物質であるドーパミンが脳内で増加するという“報酬”を得られます。
努力が必ずしも結果に結びつかないことがある現実世界と違い、ゲーム内では現実世界に比べて易しい努力の割に“報酬”を得ることができます。
脳は同程度の快楽を求める性質があるため、この“報酬”を得るためにゲームにのめり込んでしまいます。 -
2終わりがなく、刺激的なゲーム
一昔前と違い、ゲームクリア後もやりこみ要素が強いゲームや、そもそも“終わりがないインターネットゲーム”が増えています。また、テクノロジーの発達によって、ゲームの映像や特殊効果はより刺激的に進化しています。
脳はゲームを繰り返していると耐性によって感度が鈍りますが、より長時間・刺激的なゲームを求めることによって以前と同程度の快楽を求めようし、のめり込んでいきます。 -
3いつでもゲームができる環境
子供部屋にゲームがあったり、ポータブルゲームやスマホゲーム(ソシャゲ)を持っているなど、お子さんが“いつでもゲームができる環境”があるとゲームにのめり込みやすくなります。
保護者がお子さんのゲーム時間やタイミングを管理・コントロールできないと、宿題や勉強よりもゲームが優先され、ゲームに長時間没頭する可能性が高まります。 -
4発達障害・グレーゾーンの特性
「コミュニケーションが苦手」「気持ちや行動の切替が苦手」「衝動性が強い」「集中が持続できない」などの発達障害の特性がある場合、ゲーム障害(ゲーム依存症)になるリスクが高く、「友達と遊ぶよりゲームで現実逃避」「一度ゲームを始めたらやめられない」「ゲームをやりたい衝動を抑えられない」「ゲーム以外のことに集中できなくなる」などのことになりやすいです。
ゲーム環境と行動をコントロールする技術を学ぶ“ゲーム障害予防コーチング”
前述のゲーム障害(ゲーム依存症)の要因のうち、ゲームの性質に起因することは変えられないですし、一度ゲームの楽しさを知ったお子さんのゲームをやめさせるのは不可能に近いです。 ですから、「ゲームをやめさせるのではなく、保護者が生活や学業に支障が出ない範囲でコントロールしながら、ゲームを楽しませること」がコーチング1が最重要視する考え方です。
そのためには前述の「いつでもゲームができる環境」を保護者のルール作りや管理によって、環境をコントロールすることが必要となります。
また、「発達障害・グレーゾーンの特性」については、特性による行動面への影響正しく理解し、保護者が対処法を変えることで行動をコントロールすることも重要です。
コーチング1では、ゲーム障害(ゲーム依存症)になる前に、保護者がお子さんのゲーム環境と行動をコントロールする方法を学ぶ「ゲーム障害予防コーチング」を実施しています。
従来、発達障害・グレーゾーン児童の保護者向けに実施してきた子育てマネジメント「ペアレントトレーニング」をゲーム障害(ゲーム依存症)向けに再構築した独自のプログラムとなっています。
ゲーム障害(ゲーム依存症)以外にも、スマホ依存やインターネット依存にも応用可能です。
ゲーム障害予防コーチングの特徴
-
1好ましい行動を増やす行動コントロール術
「親の対処の仕方」を変えることで、お子さんの問題行動を減らし、好ましい行動を増やすことができます。
「叱る」「責める」「落胆する」などの否定的な方法でお子さんの行動をコントロールするのではなく、お子さんの問題行動の分析・分類・理解をし、「褒める」「適切な指示を出す」など肯定的な方法でお子さんの行動をコントロールする技術を学んでいきます。 -
2ゲーム障害予防のルール作り
そもそもゲーム障害(ゲーム依存症)自体への理解がないことが、「叱る」「責める」「落胆する」などの否定的な方法でお子さんをコントロールしていまう大きな原因です。
ゲーム障害(ゲーム依存症)自体への理解を深め、ゲーム環境や行動をコントロールするルール作りや管理方法、発達障害・グレーゾーンの特性に合わせた対応策を学んでいきます。 -
3発達障害・グレーゾーンの特性への対応
なぜ「コミュニケーションが苦手」「こだわりが強い」「行動コントロールが苦手」「衝動性が強い」などの特性が見られるのか正しく理解していないと、あっという間にお子さんはゲーム障害(ゲーム依存症)予備軍になってしまいます。
発達検査の結果やカウンセリングによってお子さんの特性を把握し、特性に合わせた対応策を学んでいきます。 -
4“全国対応”全10回の通信教育プログラム
・全国対応の通信教育サービス
・受講形式は「通塾」「Skype等」「電話」と選択可能
・全10回(1回あたり30分から45分程度)のプログラム構成
・受講頻度は「週1回」「隔週1回」「月1回」と選択可能
・完全マンツーマンで、質疑応答が自由
・スマホ依存やネット依存にも応用可能
・「プログラミング」と併用すると効果的
ゲーム障害予防コーチングのカリキュラム
- 1ゲーム障害について知る
- 2ゲームに関する行動を3種類に分ける
- 3褒めることによって行動を変える
- 4無視によって好ましくない行動を減らす(前編)
- 5無視によって好ましくない行動を減らす(後編)
- 6効果的な指示で行動をコントロールする(前編)
- 7効果的な指示で行動をコントロールする(後編)
- 8警告とペナルティ
- 9ゲームに関するルール作り
- 10ゲームに関する行動の徹底管理
ゲーム障害予防コーチングの申し込みは下記の登録フォームから!